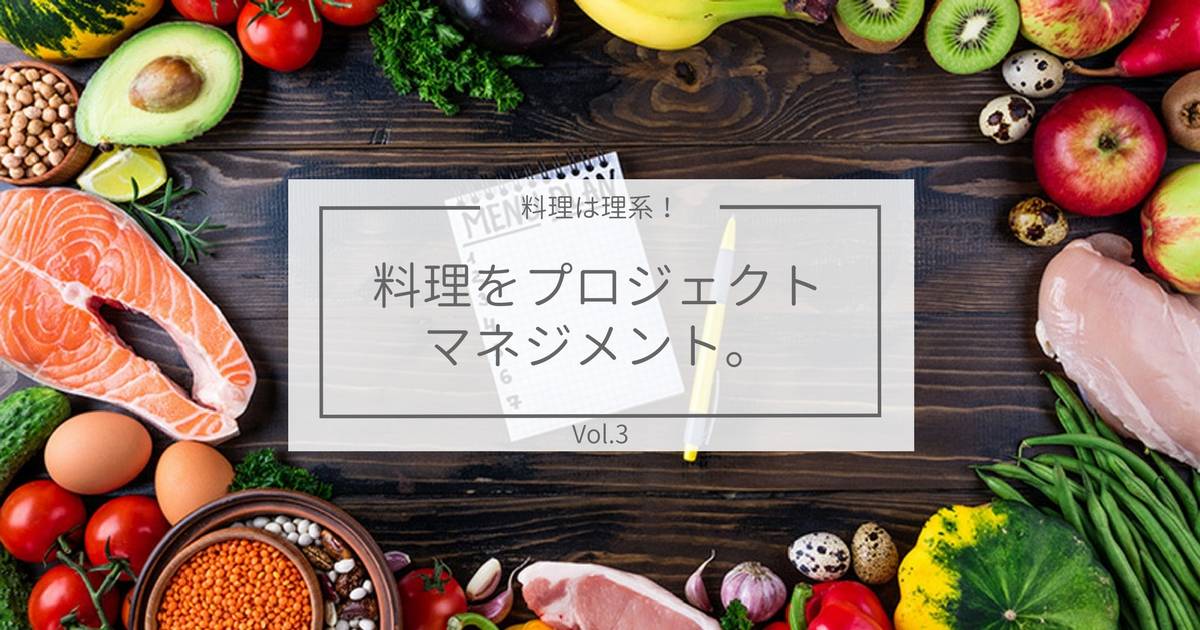
プロジェクトマネジメント的思考で料理のメニューを決めてみよう!
プロジェクト成功の鍵は上流工程。顧客(食べる人)の要求から要件定義(メニュー)と計画立案(レシピ)まで
前回は料理とプロジェクトの共通点を紹介しました。
▼前回の記事はこちら
今回から料理をプロジェクトとしてマネジメントする方法を考えていきます。
料理プロジェクトを始めるために、まずはどんな料理を作るのかメニューを決めましょう。
目次[非表示]
プロジェクトの成功の鍵は上流工程
上流工程とは
ハードウェアやソフトウェア開発の工程の流れのなかで初期の段階に行われること。一般的には、顧客の要求から仕様を決定し、大まかな設計をするまでの工程を指す。これに対して、実際の開発や製造を下流工程という。システム全体の規模や、開発にかかる期間やコストなども、上流工程で決定される。通常、開発中に問題が発生しても、仕様の変更や後戻りは難しく、特に大規模な開発では上流工程では緻密な設計が求められる。
出典 ASCII.jpデジタル用語辞典
これを料理に当てはめると、
上流工程:食べる人(顧客)の要求からメニュー(仕様)を決定し、レシピ(大まかな設計)を考える工程
下流工程:実際の調理
となります。
プロジェクトでは開発が進んでからの仕様変更や後戻りが難しく上流工程の設計が大切です。料理もプロジェクトマネジメント的思考で最初のメニュー選択とレシピをしっかり決めてから始めましょう。
1-1.食べる人(クライアント)のニーズをヒアリングして顧客満足度を上げる
プロジェクトにおけるクライアントへのヒアリングは、料理では食べる人や家族とのコミュニケーションです。プロジェクトも料理もクライアントニーズを引き出して仕様(メニュー)を決めることで満足度も高まります。
いわゆる男料理にありがちな「俺のこだわりの味」を味わえと押し付けるような料理ではダメです。相手がどんなものを食べたいのか、好きな料理、苦手な食材、昼に食べたものは何かなど丁寧にヒアリングしましょう。
しかしクライアントの要望を聞いてばかりでは、好き勝手で実現が難しいことも要求してきます。食べたい料理を聞いても「なんでもいいよ」「美味しいもの」と答えが漠然としていたり、子どもに聞いたら毎回「ハンバーク!」と答えるなんてことも。
かといって冷蔵庫にある食材で適当にちゃちゃっと作ったら、
「味は悪くないけれど今日は違う気分だった」「今日の給食でも同じ料理が出たよ」とか。
せっかく作っても喜んで食べてもらえなかったり、食べ残しが生じて翌日に処分する羽目になるのは残念です。
1-2.潜在的なニーズを引き出す
『「空腹」は最高の調味料である』と言われます。
食事を楽しむ一番の方法は食べたいものを食べること。「食べたいもの」と「好きなもの」は違います。
料理を口にして五臓六腑に染み込む感覚を味わったことがある人も多いかと思います。
疲れている時には甘いものが食べたくなるように、その時の体の状態によって美味しいと感じる栄養素は異なります。心が欲しているものは体が欲しているものでもあり、肉が食べたい時は体がタンパク質や鉄分を欲しています。特定の食材が食べたくなった時は、その食材に含まれる栄養素を欲しているのです。逆に、好きなものを食べても脳が欲している栄養でなければ、満足度は低くなります。
「昨日は肉だったから魚にしようか」
「昼食にガッツリ食べたなら夜はさっぱりした料理にしよう」
「今日は寒いから温まる料理はどうかな」
ただ相手の要求を聞くだけではなく、要求の裏にある潜在的なニーズを読み取り、メニューを提案しましょう。
2.“ニーズ・シーズ・ウォンツ”で献立を決める
商品開発で失敗しないためには、事前のマーケティングや市場調査が重要です。そこでマーケティングでおなじみの「ニーズ」「ウォンツ」「シーズ」で分析してメニューを考えてみましょう。
■マーケティングと料理のニーズ・シーズ・ウォンツ
ニーズ(Needs)
このクライアントニーズは前述の1でヒアリングした「好きなもの」です。
ウォンツ(Wants)
商品開発をする際、デザインにこだわったりブランディングに力を入れて性能以上の付加価値や訴求力を高めることをします。
料理においても『日本料理は目で食べる』と言われるように、料理そのものの味だけでなく、視覚による先入観が味覚にも大きな影響を与えています。料理ごとに合う食器を変えたり、具材の切り方や盛り付けを工夫するなどの技巧が発展したのも日本ならではの食文化です。
家庭でも時にはワンプレートでカフェっぽく、時には大皿で山盛りにしてパーティ風にするなどの変化を付けるのもいいですね。テーブルコーディネートや食事の雰囲気をこだわるのも付加価値を生み出して、食卓が豊かになります。
前述の「食べたいもの」も潜在的な欲求を満たすウォンツの一つですが、子どもにとって成長に必要な栄養素でも、好き嫌いが激しくて好きなものしか食べてくれないというケースもあります。
・彩りのある食材を用いて食欲をそそらせる
・楽しんで食事ができるように、キャラ弁やデコ料理を作る
・小さく刻んだり、煮込んだりして、見た目や味をごまかす
どのようにして子どもが嫌いな野菜を食べさせるか。親の永遠の悩みですが、これらの工夫もウォンツといえます。
シーズ(Seeds)
新しい技術や素材から制作可能となった新商品を開発することを「シーズ志向」と呼びます。
料理なら、圧力鍋で柔らかく煮た角煮、ウォーターオーブンレンジで減塩・油分カットした焼き魚、ノンフライ調理器(コンベクションオーブン)で作った揚げない唐揚げなど、新しい調理道具や家電を使ったメニューがシーズ志向の料理といえます。
料理の大きな悩みの一つは毎日の献立を考えることですが、マンネリ化しないためにもニーズ・シーズ・ウォンツを上手く取り入れてメニュー作りをしましょう。
3.“スコープ管理”で今作れる料理レシピを決める
家族(クライアント)から要求やニーズをヒアリングしてメニューの方向性が定まったら、次はスコープを決めます。
スコープ(scope)とは「『要求(やりたいこと)』から『要件化(やれること)』された成果物とタスクの対象範囲」のこと。プロジェクトでは出てきた様々な要求やアイデアを集約し成果物を決めていきますが、予算や技術の都合で機能を取捨選択して仕様を決定します。成果物もすべて一から自社で制作するのではなくて、既存のシステムを流用したり、アウトソースするなどタスクを調整します。
これを料理に当てはめると、前述のヒアリング〜マーケティングを通して“どんな料理を何品作れるか”最終的なメニューを考えて、食事の時間までにどう効率的に作るのかレシピを調整することがスコープです。
料理もレシピ通りに作っていたら食事の時間が遅くなってしまう場合もあります。
そんな時は、レシピの流れを踏まえながら、一部の工程をレンジで下ごしらえ調理したり、調理済み冷凍食品や作り置き惣菜を活用したりして、時短調理をします。時には市販の複合調味料やレトルト食品、○○の素などを使う場合もあるでしょう。
料理プロジェクトのスコープ管理では、このように状況に応じてレシピをアレンジして時短や簡単調理できるようになるのが理想です。
最初の料理プロジェクトはカレー作り
いよいよメニューを決めます。できる限り多くのニーズに応えた料理を作りたいところですが、連載1回目の記事でレシピを取り上げた「カレー」にします。
いろいろ言っておきながらカレーかい!とツッコまれそうですが、まずは分かりやすい定番メニューを例にとって料理をプロジェクトマネジメントする方法を説明します。
次回からカレーを作るプロジェクト開始です。
▼次の記事はこちら
▼すべての連載記事はこちら
『料理は理系!料理をプロジェクトマネジメント。』その他の記事はこちら>
