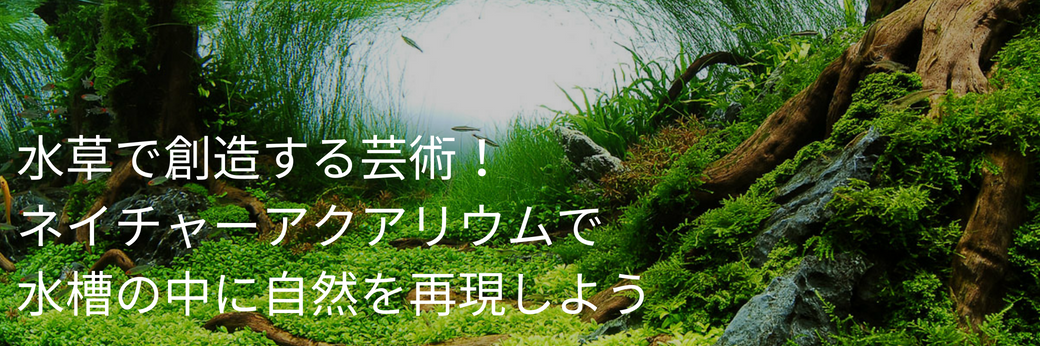目指せ釣りの達人!初心者でも大丈夫 海や川でフィッシングを楽しもう【男の趣味活】
暑い夏のお出かけスポットといえば、海や川。水遊びやバーベキューの定番だけだと飽きるので、ちょっと違った楽しみ方を開拓したいと思った時にオススメな趣味が「釣り」です。
長時間の我慢比べと挌闘の末に、狙った獲物を釣り上げた瞬間の快感は格別!
そして釣れない時は釣れない時で「別の場所に釣り場を移そう」「仕掛けを変えてみよう」と試行錯誤する過程もまた釣りの醍醐味です。
もちろん釣りというのは“釣れない時間”の方が圧倒的に長いのですが、自然の中でひたすら無心になって釣り糸をたらしているだけで、日々の疲れを忘れてリフレッシュ効果を得ることもできますよ。
とはいえ、子どもの頃に親に連れられて体験してからご無沙汰、実は釣りをしたことがない…という方もいるでしょうから、今回は釣りの基本道具やオススメの楽しみ方についてご紹介します。
必要な道具は釣り方によって変わる
簡単&シンプルなノベ竿か、投げ釣りを楽しむリール竿か
釣り竿は大きく分けて、リールをセットする「リール竿」と、リールをセットしない「ノベ竿(ルアーロッド)」の2種類になります。
ノベ竿は一般的に片手で扱えるほど軽い使いやすさが特徴的で、ライン(釣り糸)に仕掛けをセットしてあとは投げ込むだけ、と使い方もシンプル! 準備も操作も最小限で済み、初心者でもすぐに釣りを楽しむにはもってこいの竿です。
一方、リール竿はリールのセットや操作の手間がかかりますが、ノベ竿だと竿とラインを足した長さの範囲内でしか釣れないのに対し、リールに巻いたラインを投げればより遠く深くの魚も狙えます。また、ラインの長さを調節できるので、ぐいぐい引っ張る大物との挌闘にも向いています。
何はともあれ手軽に始めるか、本格的に極めていくか。まずは自分が目指す釣りのスタイルを検討してから道具揃えを始めましょう。
ノベ竿を選ぶポイントは「扱いやすさ」
ノベ竿にはいくつか種類がありますが、釣りたい場所や魚の種類に限定がなければ、川でも海でも使える万能竿がオススメ。長時間持つ間に疲れないよう重さは100g以内、また扱いやすいよう長さは4.5m前後までが無難です。
竿の他にはライン(糸)、オモリ、アタリの瞬間が分かるウキ、市販の完成仕掛け、付けエサ、魚を誘う「寄せエサ」、大きい魚をすくうためのタモ網(玉網)などを揃えておきましょう。
リール竿は釣り方や目的を絞ってから選ぼう
リール竿を選ぶ主な基準は、竿の長さとロッドパワー(竿が曲がる時の硬さ)。
竿が長いほど遠投しやすく、ロッドパワーが高いほど大型魚向けの重いルアーを投げられます。竿の種類は、汎用性の高いシーバスロッドをはじめ、釣りたい魚や使い方など目的別に細分化しているのでじっくり検討してください。
リールも釣り方に合った種類に分かれていますが、スピニングリールは用途がほとんど不問で扱いやすいので初心者にオススメですよ。
初心者でも楽しめる海と川でのオススメ釣りスタイル
■海の堤防でじっくり「ノベ竿ウキ釣り」
天然のエサが豊富な堤防のあたりにはいろいろな種類の魚が棲みつき、時には回遊魚もやって来ます。さらに足場が良くて釣りやすいという、とっておきのスポットです。
遠くまでラインを投げる必要がないのでノベ竿を使い、アジなど多くの魚種が狙えるウキ釣りを楽しんでみてください。
仕掛けを小さく動かして魚を誘い、食いついた魚の引きをダイレクトに感じ、リールの力を借りずに自分の力で釣り上げる快感はきっと病みつきになりますよ。
また、潮流がぶつかる堤防の先端や消波ブロックの近くだと、エサが多く集まるのでオススメです。
■自然の癒し効果も味わえる「渓流エサ釣り」
豊かな緑や川の中に身を置き、鳥のさえずりと爽やかな風を感じられる渓流釣りは、自然の癒し効果と釣りの楽しみを味わえ、まさに一挙両得!
水流の速さや水深によって釣れるポイントが異なるため、ただじっと待つのではなく、魚の居場所を見つける“攻め”の駆け引きが求められるのも渓流釣りの醍醐味です。まずは手軽にチャレンジできるノベ竿エサ釣りで、ヤマメやアマゴを狙ってみましょう。
釣りの基本道具やオススメの楽しみ方をご紹介してきましたが、いかがでしたか。
今回は初心者向けの手軽な釣り方を紹介しましたが、慣れてきたらボートで沖に出て多彩な魚や大物を狙ってみたり、渓流でフライフィッシングにチャレンジするのも面白そうですね。
同じ海や川でも釣りスポットは無限大だし、季節によって釣れる魚も変わるので、ぜひとも1年を通して飽きることのない魅力にハマってしまいましょう。
※立入禁止区域には決して入らず、釣り場のルールとマナーを守りましょう。
※当日の天候や、天候の変化に伴う波や水位の変化にご注意ください。
※小さな子どもと楽しむ場合は、ライフジャケットを着用させるなど安全にご配慮ください。
<参考文献>
西野弘章・監修『ゼロからのつり入門』(小学館・刊)
\その他おすすめ記事/