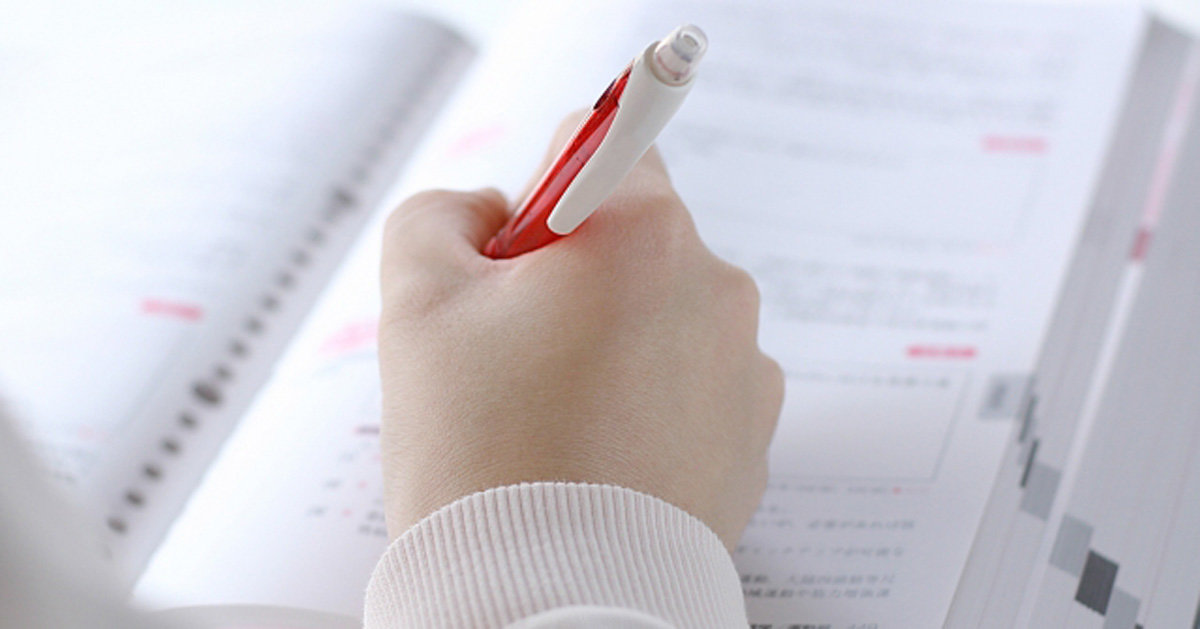
娘の進路や将来についてパパはどう関わればいい?【教えて先輩!オトコの家事育児お悩み相談室】
教育
村上誠
村上誠(NPO法人ファザーリング・ジャパン理事、秘密結社主夫の友総統)
家事や育児に日々奮闘している全国のパパたちから悩みを受け付け、経験豊富な先輩パパたちがアドバイスを贈る「教えて先輩!オトコの家事育児お悩み相談室」。
第4回の悩みに答えてくれるのは、NPO法人ファザーリング・ジャパンの理事を務め、兼業主夫として2人の子どもを育てている村上誠さんです。
第4回の悩みに答えてくれるのは、NPO法人ファザーリング・ジャパンの理事を務め、兼業主夫として2人の子どもを育てている村上誠さんです。
<相談内容>
高2と高1の姉妹の父親です。
姉は大学進学について考え始める時期に来ています。「小説を読むのが好きだから文学部に行こうかな」と言っていますが、就きたい職業などは思い浮かんでないそうです。
妹は以前から「保育士になりたい。」とは言っていますが、部活ばかりで全然家庭学習をしておらず大学に行けるような成績ではありません。
そんな二人に父親としてどう接したらよいでしょう。
(せいちゃんさん)
________________________________________
こんにちは。ファザーリング・ジャパンの村上です。
年頃の子どもの接し方は難しいですよね。特に男親と娘とはすれ違いも多く、幼い頃は「パパのお嫁さんになる」と言っていた可愛い娘が、思春期になると手のひらを返したように「うるさい」「うざい」「お父さん臭い」と父親を嫌いだしたり、洗濯や風呂を父と同じ水にしたくない、会話もろくにないといったことも珍しくありません。子どもとどう関わればいいのか悩みを抱えている父親も多いようで、私も傷心したパパ友の嘆き飲みに付き合うことがあります。
実は異性を意識する年頃の娘が父親に嫌悪感を抱くのは、遺伝子的に近親交配を避けるための本能的な反応だとも言われています。思春期・反抗期の親子関係には、乳幼児期からの親密な関わりを通して愛着形成と信頼関係の土台を育んでいるかどうかが重要となります。
子育てや教育は妻に任せっきりの父親もまだ多いと思いますが、相談者のせいちゃんさんは、娘さんと進路について話せるほどに良好な父娘関係を築いてきているのではないでしょうか。
姉は大学進学について考え始める時期に来ています。「小説を読むのが好きだから文学部に行こうかな」と言っていますが、就きたい職業などは思い浮かんでないそうです。
妹は以前から「保育士になりたい。」とは言っていますが、部活ばかりで全然家庭学習をしておらず大学に行けるような成績ではありません。
そんな二人に父親としてどう接したらよいでしょう。
(せいちゃんさん)
________________________________________
こんにちは。ファザーリング・ジャパンの村上です。
年頃の子どもの接し方は難しいですよね。特に男親と娘とはすれ違いも多く、幼い頃は「パパのお嫁さんになる」と言っていた可愛い娘が、思春期になると手のひらを返したように「うるさい」「うざい」「お父さん臭い」と父親を嫌いだしたり、洗濯や風呂を父と同じ水にしたくない、会話もろくにないといったことも珍しくありません。子どもとどう関わればいいのか悩みを抱えている父親も多いようで、私も傷心したパパ友の嘆き飲みに付き合うことがあります。
実は異性を意識する年頃の娘が父親に嫌悪感を抱くのは、遺伝子的に近親交配を避けるための本能的な反応だとも言われています。思春期・反抗期の親子関係には、乳幼児期からの親密な関わりを通して愛着形成と信頼関係の土台を育んでいるかどうかが重要となります。
子育てや教育は妻に任せっきりの父親もまだ多いと思いますが、相談者のせいちゃんさんは、娘さんと進路について話せるほどに良好な父娘関係を築いてきているのではないでしょうか。
▼あわせて読みたい
理想の父親は、威厳よりも親近感のある存在
今どきの理想の父親像は、優しくて親しみやすく理解力のある存在です。
親として子どもの進路についてあれこれ意見を言いたくなる気持ちも分かりますが、その前に子どもの話をよく聞いてください。そして、自分も若い頃同じように悩んだこと、失敗したことを正直に話してみましょう。父親が身近な存在に感じられるようになります。気をつけることは、自慢話になったり、昔の価値観を押し付けたりせず、今の時代背景を理解し子どもの考えを尊重することが大切です。
お姉さんは就きたい職業が定まらないなら、とりあえず大学に進学してみるのもいいと思います。大学での専門的な学びを通して視野が広がれば、おのずとやりたい仕事が見えてくるでしょう。妹さんは保育士を志望しているなら、4年制大学だけでなく、短大や専門学校にも保育士養成学校はありますし、通信教育で学ぶことも可能です。
今や終身雇用は過去の遺物。一つの仕事や職場にこだわらず転職するのもよくあるキャリアパスです。時代の変化に応じて、テレワーク、ノマド、副業解禁など働き方も多様化しています。やりたいことや仕事は変わるものと柔軟な考えを持ち、大学への進学も人生の通過点の一つとして捉えていいのではないでしょうか。
親として子どもの進路についてあれこれ意見を言いたくなる気持ちも分かりますが、その前に子どもの話をよく聞いてください。そして、自分も若い頃同じように悩んだこと、失敗したことを正直に話してみましょう。父親が身近な存在に感じられるようになります。気をつけることは、自慢話になったり、昔の価値観を押し付けたりせず、今の時代背景を理解し子どもの考えを尊重することが大切です。
お姉さんは就きたい職業が定まらないなら、とりあえず大学に進学してみるのもいいと思います。大学での専門的な学びを通して視野が広がれば、おのずとやりたい仕事が見えてくるでしょう。妹さんは保育士を志望しているなら、4年制大学だけでなく、短大や専門学校にも保育士養成学校はありますし、通信教育で学ぶことも可能です。
今や終身雇用は過去の遺物。一つの仕事や職場にこだわらず転職するのもよくあるキャリアパスです。時代の変化に応じて、テレワーク、ノマド、副業解禁など働き方も多様化しています。やりたいことや仕事は変わるものと柔軟な考えを持ち、大学への進学も人生の通過点の一つとして捉えていいのではないでしょうか。
▼あわせて読みたい
2020年教育改革。家庭でも実践
近年、男性向けビジネス雑誌でも盛んに教育や受験の特集が組まれるなど、教育にも関心を持つ父親が増加しています。
教育といえば2020年に本格化する教育改革。「アクティブラーニング」「プログラミング教育」「英語4技能」といったキーワードを最近よく聞きませんか? ちょうど高2のお姉さんが大学入試を迎える2021年からセンター試験が「大学入学共通テスト」に変わり、「知識の理解の質が問われ、思考力・判断力・表現力を活用して解く」ことが一層重視されるようになります。
なぜ教育が変わるかというと、グローバル化、産業構造や就業構造の変化などに伴い、世の中で求められる力が変わって来ているから。21世紀型能力と言われる、生きる力、コミュニケーション能力といった非認知能力を身につけることが求められています。今までの知識偏重の詰め込み型の勉強では時代の変化に対応しきれませんので、「勉強しなさい」と言うだけでは十分ではありません。
日頃から「能動的、批判的に考える習慣」を養うためには、ニュースなどの身近な話題やグローバルな問題を家族で話す、生活で気づいた疑問や課題を教科と結びつけるといった、親子で一緒に学ぶ姿勢が大切です。
週に何日かは仕事を早く切り上げて帰宅し、家族で一緒に食事をしながら会話する団らんの時間を作り、アクティブラーニング(主体的・対話的な学び)を家庭で実践するといいでしょう。娘さんたちと屈託のない日常会話ができていれば、進路や将来についても自然に話せるようになると思います。
教育といえば2020年に本格化する教育改革。「アクティブラーニング」「プログラミング教育」「英語4技能」といったキーワードを最近よく聞きませんか? ちょうど高2のお姉さんが大学入試を迎える2021年からセンター試験が「大学入学共通テスト」に変わり、「知識の理解の質が問われ、思考力・判断力・表現力を活用して解く」ことが一層重視されるようになります。
なぜ教育が変わるかというと、グローバル化、産業構造や就業構造の変化などに伴い、世の中で求められる力が変わって来ているから。21世紀型能力と言われる、生きる力、コミュニケーション能力といった非認知能力を身につけることが求められています。今までの知識偏重の詰め込み型の勉強では時代の変化に対応しきれませんので、「勉強しなさい」と言うだけでは十分ではありません。
日頃から「能動的、批判的に考える習慣」を養うためには、ニュースなどの身近な話題やグローバルな問題を家族で話す、生活で気づいた疑問や課題を教科と結びつけるといった、親子で一緒に学ぶ姿勢が大切です。
週に何日かは仕事を早く切り上げて帰宅し、家族で一緒に食事をしながら会話する団らんの時間を作り、アクティブラーニング(主体的・対話的な学び)を家庭で実践するといいでしょう。娘さんたちと屈託のない日常会話ができていれば、進路や将来についても自然に話せるようになると思います。
働くことのワクワクを伝えよう
将来、子どもの65%が今はない仕事に就き、逆に今の仕事の49%がAIに代替されると推測されています。子どもたちは予測できない未来に対して「不安」と「ワクワク」のどちらが強いでしょうか。
子どもにとって一番身近な社会人は親です。昔の日本は住職近接が多く、子どもも家業を手伝うなど親が仕事をしている姿を目にする機会が日常的にありました。現代は大半がサラリーマン家庭で、仕事が忙しくて家庭に不在気味の父親も多いのではないでしょうか。もし、疲れて帰って来るくたびれた父親の姿しか見ていないなら、子どもが働くことに対してポジティブなイメージを持つことは難しいですね。
そこで親自らが、資格を取得するために勉強したり、スキルアップのために新しいことにチャレンジするといった仕事への前向きな姿勢を見せる。仕事のやりがいや楽しさ、働くことの「ワクワク」を伝えることが大切です。
新しい学習指導要領では、困難な時代を生き抜くために身につけてほしい力として、「1.社会の変化に受け身で対処するのではなく、2.自ら課題を発見し、他者と協働してその解決を図り、3.新しい知・価値を創造する力」を掲げています。これって仕事でも求められている力ですよね。
あなたはどのような人と一緒に仕事がしたいですか? 社会で必要とされ、活躍している人物像を考えてみてください。子どもの就く職業ではなく、子どもがどのような人になってほしいかを基準にすると良いと思います。
将来、娘さんたちが成人して社会人になった時、一緒にお酒を飲みながら仕事や人生の相談にも乗れるのは親としての醍醐味だと思います。そのような頼れる父親になれるように、今から良い関係を築けるといいですね。
本企画では、家族をもつ男性からのお便りをお待ちしております!
投稿いただいたお便りの中から採用されたものは、本企画にて家事育児のプロがお悩みにお答えいたします!
みなさまからのお便り、お待ちしております!
子どもにとって一番身近な社会人は親です。昔の日本は住職近接が多く、子どもも家業を手伝うなど親が仕事をしている姿を目にする機会が日常的にありました。現代は大半がサラリーマン家庭で、仕事が忙しくて家庭に不在気味の父親も多いのではないでしょうか。もし、疲れて帰って来るくたびれた父親の姿しか見ていないなら、子どもが働くことに対してポジティブなイメージを持つことは難しいですね。
そこで親自らが、資格を取得するために勉強したり、スキルアップのために新しいことにチャレンジするといった仕事への前向きな姿勢を見せる。仕事のやりがいや楽しさ、働くことの「ワクワク」を伝えることが大切です。
新しい学習指導要領では、困難な時代を生き抜くために身につけてほしい力として、「1.社会の変化に受け身で対処するのではなく、2.自ら課題を発見し、他者と協働してその解決を図り、3.新しい知・価値を創造する力」を掲げています。これって仕事でも求められている力ですよね。
あなたはどのような人と一緒に仕事がしたいですか? 社会で必要とされ、活躍している人物像を考えてみてください。子どもの就く職業ではなく、子どもがどのような人になってほしいかを基準にすると良いと思います。
将来、娘さんたちが成人して社会人になった時、一緒にお酒を飲みながら仕事や人生の相談にも乗れるのは親としての醍醐味だと思います。そのような頼れる父親になれるように、今から良い関係を築けるといいですね。
本企画では、家族をもつ男性からのお便りをお待ちしております!
投稿いただいたお便りの中から採用されたものは、本企画にて家事育児のプロがお悩みにお答えいたします!
みなさまからのお便り、お待ちしております!

