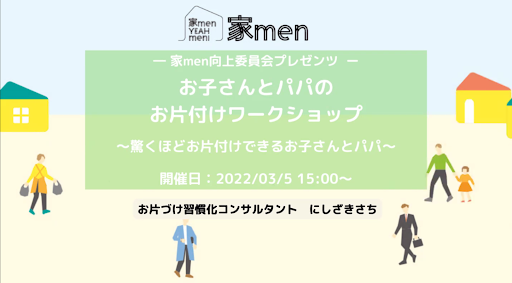
【ワークショップレポート】お子さんとパパで一緒にお片付け!「おかたづけのきほん」と家族円満のコツ
ライフスタイル
目次[非表示]
家men読者の皆さんは、片付けは得意でしょうか?それとも苦手でしょうか?
また、お子さんにはどのようにして片付けをするように伝えていますか?
本屋さんに行くと、たくさんの「片付け」に関する本が並んでいますよね。きっと多くの方が整理整頓が苦手だったり、1回片付けてもすぐ散らかってしまう…などの悩みを抱えていることの裏付けでもあると思います。
でも、「片付け」ってただ「部屋がきれいになる」以外にも得られることが実はたくさんあることをご存じでしょうか。
今回、家men向上委員会主催オンラインイベント「お子さんとパパのお片付けワークショップ」に家men編集部も参加。親子での片付けの取り組み方、そして片付けを通じて身につく力や効果を、お片づけ習慣化コンサルタントの西崎さんに教えていただきました。
<今回教えていただいた先生はこの方!>
また、お子さんにはどのようにして片付けをするように伝えていますか?
本屋さんに行くと、たくさんの「片付け」に関する本が並んでいますよね。きっと多くの方が整理整頓が苦手だったり、1回片付けてもすぐ散らかってしまう…などの悩みを抱えていることの裏付けでもあると思います。
でも、「片付け」ってただ「部屋がきれいになる」以外にも得られることが実はたくさんあることをご存じでしょうか。
今回、家men向上委員会主催オンラインイベント「お子さんとパパのお片付けワークショップ」に家men編集部も参加。親子での片付けの取り組み方、そして片付けを通じて身につく力や効果を、お片づけ習慣化コンサルタントの西崎さんに教えていただきました。
<今回教えていただいた先生はこの方!>
西崎 彩智(にしざき さち)
お片づけ習慣化コンサルタント・株式会社Homeport 代表取締役
片づけ・自分の人生・夫婦間のコミュニケーションを軸にママたちが自分らしくご機嫌な毎日になる『家庭力アッププロジェクト®︎』を主宰。
またライフワークとして、子どもたちが片づけを通して”生きる力”を養える『親子deお片づけ』も主宰。
お片づけ習慣化コンサルタント・株式会社Homeport 代表取締役
片づけ・自分の人生・夫婦間のコミュニケーションを軸にママたちが自分らしくご機嫌な毎日になる『家庭力アッププロジェクト®︎』を主宰。
またライフワークとして、子どもたちが片づけを通して”生きる力”を養える『親子deお片づけ』も主宰。
親子で一緒に片付けに取り組もう
今回は親子4組が参加。まず冒頭30分で、パパと子どもが一緒に「親子でどのようにお片付けに取り組んでいく?」かを考えながら、「おかたづけのきほん」を学んでいきました。
「どうやってものを”わけて”、どのように”しくみ”を作って、どうやって”ルールをつくって”いけばいいの? パパと一緒に考えてみよう!」と、この3ステップを西崎さんが丁寧に子どもたちに説明。子どもはオンラインセミナーでは集中力が30分ほどしか続かないためわかりやすく説明をし、毎日すぐにできる宿題を出して、ここからはパパへの「片付け」に関するレクチャーに移ります。
でもこのレクチャー、「どこにどうモノを片付けすればいい」「どうやって残すモノを選ぶ」などのよくあるお片付け本とは全く異なりました!その様子をちらっとご紹介いたします…!
でもこのレクチャー、「どこにどうモノを片付けすればいい」「どうやって残すモノを選ぶ」などのよくあるお片付け本とは全く異なりました!その様子をちらっとご紹介いたします…!
片付けをすることで、子どもの生きる力を育てる
西崎さんが取り組んでいる「家庭力アッププロジェクト🄬」。過去に1,500人以上の修了生がいらっしゃるそうです。海外からオンラインでレッスンに参加する方もいるくらい人気のプロジェクト。多くの生徒に教えながら見えてきたものを、西崎さんは図を用いながら、パパたちにロジカルに説明してくれました。
レッスンの修了生やそのご家族からの感想で特に印象的だったのは、部屋がきれいになる…ということだけではなく「片付けをすることでいろんな力が身につく」とのことでした。
西崎さんいわく、「片付けは生きる力を育てる」ということ。
片付けをするための段取り力、モノがいるかいらないかを判断する決断力、残ったモノを大切にする力、そして頭の中で考えたことを行う行動実践力、それらがお片付けにより身につく、ということ。たしかに片付けのステップを一つひとつクローズアップすると、あらゆるスキルが必要になる気がします。
実際、オフィスで仕事をすることを考えてみても、片付けることで仕事のパフォーマンスが上がった経験や、また、片付けができる人の仕事の段取りがてきぱきしている…そんなことを思ったことはありませんか。西崎さんの説明が実際にあった事例をあげながら片付けの必要性について紹介されていたので、参加しているパパたちは大きくうなずく様子も。
また、西崎さんが紹介した事例の中で、大学生の行動変容を調べたところ、「片付けなさい」と言われるだけだと指示待ち人間になってしまう傾向がある、という興味深いお話もありました。近年、社会も大きく変わってきており、「個性」「行動力」がこれまでよりも評価されるようになってきましたよね。これからの子どもに必要なのは「指示される前に考えて動く力」。パパたちもこの行動観察の結果を聞いて、片付けが持つ力をあらためて認識し、理解を深めていました。
>次ページへ 「片付けて!」が通じない理由
西崎さんいわく、「片付けは生きる力を育てる」ということ。
片付けをするための段取り力、モノがいるかいらないかを判断する決断力、残ったモノを大切にする力、そして頭の中で考えたことを行う行動実践力、それらがお片付けにより身につく、ということ。たしかに片付けのステップを一つひとつクローズアップすると、あらゆるスキルが必要になる気がします。
実際、オフィスで仕事をすることを考えてみても、片付けることで仕事のパフォーマンスが上がった経験や、また、片付けができる人の仕事の段取りがてきぱきしている…そんなことを思ったことはありませんか。西崎さんの説明が実際にあった事例をあげながら片付けの必要性について紹介されていたので、参加しているパパたちは大きくうなずく様子も。
また、西崎さんが紹介した事例の中で、大学生の行動変容を調べたところ、「片付けなさい」と言われるだけだと指示待ち人間になってしまう傾向がある、という興味深いお話もありました。近年、社会も大きく変わってきており、「個性」「行動力」がこれまでよりも評価されるようになってきましたよね。これからの子どもに必要なのは「指示される前に考えて動く力」。パパたちもこの行動観察の結果を聞いて、片付けが持つ力をあらためて認識し、理解を深めていました。
>次ページへ 「片付けて!」が通じない理由



