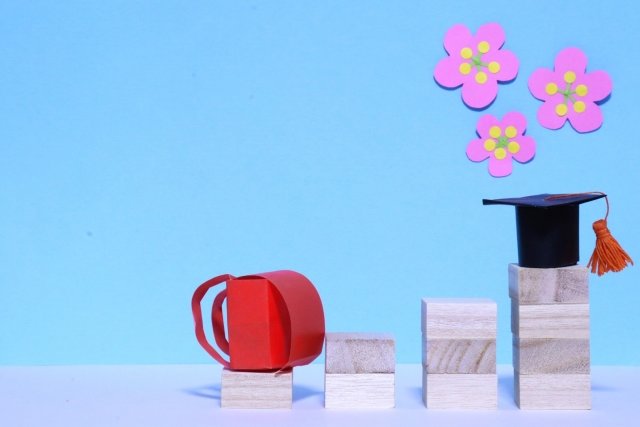【家計管理を始めたい人必見】6つのステップですぐ始められる家計管理のコツ
マネー・保険
目次[非表示]
※この記事は2020年1月に公開された記事を再編集・再公開しています
毎日の暮らしの「困った!」に役立つ技やコツをご紹介する連載「目指せ我が家のHERO!家族を助ける特技を作る」。今回のテーマは「家計管理」です。
結婚し子どもが生まれると、出産、子育て、マイホームと人生のステージごとにある程度のお金がかかります。その時に備えてしっかり計画的に貯蓄しておきたいけど、家計の管理は面倒なのでつい手付かずのまま…。
このままでは将来が不安という皆さんのために今回は、All About家計簿・家計管理ガイドの二宮清子さんに、家計管理のコツや押さえるべきポイントを分かりやすく解説してもらいます。この機会に家計管理について考えてみませんか。
結婚し子どもが生まれると、出産、子育て、マイホームと人生のステージごとにある程度のお金がかかります。その時に備えてしっかり計画的に貯蓄しておきたいけど、家計の管理は面倒なのでつい手付かずのまま…。
このままでは将来が不安という皆さんのために今回は、All About家計簿・家計管理ガイドの二宮清子さんに、家計管理のコツや押さえるべきポイントを分かりやすく解説してもらいます。この機会に家計管理について考えてみませんか。
家計管理はなぜ必要?
なぜ、ちゃんと家計を管理する必要があるのか?と聞かれれば、「必要な時に必要なお金を支払えるようにするため」と言えます。例えば、子どもが挑戦したいことや学校への進学に「お金がない」ことを理由に諦めさせることほど、親にとって辛いことはありません。
だからこそ、必要な時に必要なお金が準備できるようにするためには、ある程度のライフプランや教育方針を立て、必要な金額を予算立ててそれらに向けて準備していく必要があります。
今月のお給料をすべて生活費や欲しい物にあてていては、未来に必要になるお金が準備できません。そこで、教育費〇万円、マイホーム資金〇円…と計画的に貯蓄をしていくことが求められます。
だからこそ、必要な時に必要なお金が準備できるようにするためには、ある程度のライフプランや教育方針を立て、必要な金額を予算立ててそれらに向けて準備していく必要があります。
今月のお給料をすべて生活費や欲しい物にあてていては、未来に必要になるお金が準備できません。そこで、教育費〇万円、マイホーム資金〇円…と計画的に貯蓄をしていくことが求められます。
家計管理のメリット――子どもの金銭教育につながる
家計管理を始めると、物の値段に敏感になったり、価値と値段の違いに気付く、メリハリのある使い方でできるようになるなど、金銭感覚が磨かれていきます。
こうして磨かれた親自身の金銭感覚は、子どもの金銭感覚のベースになります。つまり子どもに良い金銭教育を与え経済的自立を果たしてほしいと思うなら、まずは親がしっかりとした金銭感覚を身に付けることが求められるのです。
こうして磨かれた親自身の金銭感覚は、子どもの金銭感覚のベースになります。つまり子どもに良い金銭教育を与え経済的自立を果たしてほしいと思うなら、まずは親がしっかりとした金銭感覚を身に付けることが求められるのです。
家計管理を始めるための6ステップ
STEP1:現状把握(収入・支出などを洗い出す)
家計管理を始める時のファーストステップは「現状把握」です。収入・支出・資産・負債・保険など分かる範囲で良いので洗い出していきましょう。
収入…給与やボーナスの手取り額、児童手当等
支出…わかる範囲で書き出しましょう
資産…預貯金、学資保険・個人年金・終身保険等の貯蓄型保険、確定拠出年金、持株会
投資信託、株式等の金融商品等
負債…奨学金、車のローン、住宅ローン、クレジットカードの支払い等
保険…自動車保険、火災保険、生命保険、医療保険等
この時に、「金額や内容が把握できない項目」があることに気付くこともあるかと思いますが、それで大丈夫です。分からない&把握できないことが何なのかが分かれば、何を知り把握すれば良いのか分かるので、スタートラインに立ったと言えます。
収入…給与やボーナスの手取り額、児童手当等
支出…わかる範囲で書き出しましょう
資産…預貯金、学資保険・個人年金・終身保険等の貯蓄型保険、確定拠出年金、持株会
投資信託、株式等の金融商品等
負債…奨学金、車のローン、住宅ローン、クレジットカードの支払い等
保険…自動車保険、火災保険、生命保険、医療保険等
この時に、「金額や内容が把握できない項目」があることに気付くこともあるかと思いますが、それで大丈夫です。分からない&把握できないことが何なのかが分かれば、何を知り把握すれば良いのか分かるので、スタートラインに立ったと言えます。
STEP2:ライフプランを立てる
どのような人生を送りたいのかをご夫婦・ご家族で話し合いましょう。教育方針やマイホームの購入時期、仕事はどうするのか、旅行や趣味など、自分と家族の大好きなことにお金を使うのも忘れてはいけません。
ライフプランが立つと、いつまでにいくら必要になるのかが明確になるため、貯蓄の計画も立てやすくなります。
ライフプランが立つと、いつまでにいくら必要になるのかが明確になるため、貯蓄の計画も立てやすくなります。
STEP3:目標貯蓄額を決める
今後、いつ、何に、いくら、かかるのかわかれば、次は貯蓄計画です。毎月いくら貯蓄できるのか? ボーナスからいくら貯蓄できるのか? そして、どこにいくら貯めていくのか?も検討しましょう。
以下のように、100万円を貯めるのにも、分散させて貯めることはお金を守ることにもつながります。
<目標年間貯蓄額100万円の貯蓄計画例>
・預貯金 毎月1万円(ボーナス時20万円×2回)
・一般財形 毎月1万円(ボーナス時3万円×2回)
・学資保険 毎月1万5千円
・積立型の投資信託 毎月1万円
以下のように、100万円を貯めるのにも、分散させて貯めることはお金を守ることにもつながります。
<目標年間貯蓄額100万円の貯蓄計画例>
・預貯金 毎月1万円(ボーナス時20万円×2回)
・一般財形 毎月1万円(ボーナス時3万円×2回)
・学資保険 毎月1万5千円
・積立型の投資信託 毎月1万円
STEP4:予算を立てる
貯蓄の計画が立てば、次に生活費の予算を立てます。豊かになる公式は「収入-貯蓄=生活費」というように先取り貯蓄の習慣を身に付け、残ったお金で生活をすることです。
その生活費の中で何にいくら使うのかを決めていきましょう。この金額に無理がある場合には、生活費の無駄を省いたり、収入を上げるという努力が必要になります。
その生活費の中で何にいくら使うのかを決めていきましょう。この金額に無理がある場合には、生活費の無駄を省いたり、収入を上げるという努力が必要になります。
STEP5:家計簿で支出を把握する
現状把握の時に、口座引落しやクレジットカード払いのものは金額が把握できても、食費など現金払いの支出に関しては何にいくら使っているのか分からない…といった使途不明金も多いことに気付いたのではないでしょうか?
私のこれまでの家計相談の経験から言うと、一般のご家庭で使途不明金は年間100万円前後になる場合が多く、この使途不明金を解消するためにも家計簿は必須となります。
家計管理が上手くいくコツは「支出」を管理できるようになること。そのためには家計簿で支出を把握する必要があります。
<家計簿が長続きするコツ>
① 家計簿には手書きやアプリ、エクセルで管理等、いろいろと種類がありますが、簡単そうなものから始めてみましょう。好みや向き不向きもあるので、自分に合う家計簿が見付かるまではいろいろと試してみましょう。
② 家計簿は「できるだけ手間を省くこと」が長続きのコツです。会社の会計ではないので1円単位でつける必要はなく、日単位では「1/10 食費1,500円、医療費2,300円」、月単位では「1月 食費53,000円、医療費8,000円」というように100円、1,000円単位で問題ありません。従って先月の残高と合わせる必要もありません。
③ 手書きやエクセルで管理する場合、毎日帰宅したらレシートを財布から出し、項目ごとに分けたジャバラになったファイルに入れておきましょう。そして1ヵ月が終わったら集計し、記帳した通帳、クレジットカードの明細も足して1ヵ月の支出を項目ごとに記入します。
私のこれまでの家計相談の経験から言うと、一般のご家庭で使途不明金は年間100万円前後になる場合が多く、この使途不明金を解消するためにも家計簿は必須となります。
家計管理が上手くいくコツは「支出」を管理できるようになること。そのためには家計簿で支出を把握する必要があります。
<家計簿が長続きするコツ>
① 家計簿には手書きやアプリ、エクセルで管理等、いろいろと種類がありますが、簡単そうなものから始めてみましょう。好みや向き不向きもあるので、自分に合う家計簿が見付かるまではいろいろと試してみましょう。
② 家計簿は「できるだけ手間を省くこと」が長続きのコツです。会社の会計ではないので1円単位でつける必要はなく、日単位では「1/10 食費1,500円、医療費2,300円」、月単位では「1月 食費53,000円、医療費8,000円」というように100円、1,000円単位で問題ありません。従って先月の残高と合わせる必要もありません。
③ 手書きやエクセルで管理する場合、毎日帰宅したらレシートを財布から出し、項目ごとに分けたジャバラになったファイルに入れておきましょう。そして1ヵ月が終わったら集計し、記帳した通帳、クレジットカードの明細も足して1ヵ月の支出を項目ごとに記入します。
STEP6:定期的に夫婦で確認し合う
現状把握やライフプラン、貯蓄や生活費の予算立ては必ず夫婦一緒に行います。家計簿に関しては、得意不得意、時間の有無があるので話し合って決めましょう。
そして、定期的に夫婦で数字を確認し合うことが大切です。家計管理は夫婦で力を合わせて取り組むことができれば素晴らしく改善され、資産形成も進みます。反対にどちらか一方だけで取り組むには肩の荷が重くストレスとなり、思うように改善されません。
我が家も家計を立て直す時、夫にどうしても協力してもらいたくて、家計や自分達と子ども達の未来について話し合いました。夫が「家計の事は知るのが怖かった」と言ったのが今でも忘れられません。現実を受け止めるには勇気がいるんですね。しかし、夫婦で力を合わせ人生のハードルを乗り越え夢をひとつずつ形にしていくと、未来に希望が持て、「何があってもこの人と一緒なら大丈夫」という安心と自信がつき、これまで以上の信頼関係が築けました。
妻にどのように相談すれば悩んだら「将来のために家計について話し合いたい」と話し合いの場を設けましょう。家族を大切に思っているなら、話し合いに応じてくれるはずです。二人で歩んでください。
そして、定期的に夫婦で数字を確認し合うことが大切です。家計管理は夫婦で力を合わせて取り組むことができれば素晴らしく改善され、資産形成も進みます。反対にどちらか一方だけで取り組むには肩の荷が重くストレスとなり、思うように改善されません。
我が家も家計を立て直す時、夫にどうしても協力してもらいたくて、家計や自分達と子ども達の未来について話し合いました。夫が「家計の事は知るのが怖かった」と言ったのが今でも忘れられません。現実を受け止めるには勇気がいるんですね。しかし、夫婦で力を合わせ人生のハードルを乗り越え夢をひとつずつ形にしていくと、未来に希望が持て、「何があってもこの人と一緒なら大丈夫」という安心と自信がつき、これまで以上の信頼関係が築けました。
妻にどのように相談すれば悩んだら「将来のために家計について話し合いたい」と話し合いの場を設けましょう。家族を大切に思っているなら、話し合いに応じてくれるはずです。二人で歩んでください。
家計管理と聞くと「大変そう」というイメージがあるかもしれませんが、自分と家族を守り幸せと豊かさにつながる大切な作業だと気付くはず。まずはパパが率先し、そして夫婦で協力しながら一歩ずつ進んでいきましょう。
<専門家プロフィール>
All About家計簿・家計管理ガイド
二宮 清子さん(https://allabout.co.jp/gm/gp/1104/)
合同会社リーフ代表。専業主婦時代に赤字家計に転落したことをきっかけに、節約、貯蓄、投資の重要性に目覚めてFP資格を取得。赤字家計を脱出した自分の体験から、節約や家計簿についてのアイデアを発信している。2011年に独立系FP事務所「幸せマネープラン」を開業。その後「合同会社リーフ」を設立。
連載『目指せ!我が家のHERO-家族を助ける特技を作る-』記事一覧
<専門家プロフィール>
All About家計簿・家計管理ガイド
二宮 清子さん(https://allabout.co.jp/gm/gp/1104/)
合同会社リーフ代表。専業主婦時代に赤字家計に転落したことをきっかけに、節約、貯蓄、投資の重要性に目覚めてFP資格を取得。赤字家計を脱出した自分の体験から、節約や家計簿についてのアイデアを発信している。2011年に独立系FP事務所「幸せマネープラン」を開業。その後「合同会社リーフ」を設立。
連載『目指せ!我が家のHERO-家族を助ける特技を作る-』記事一覧