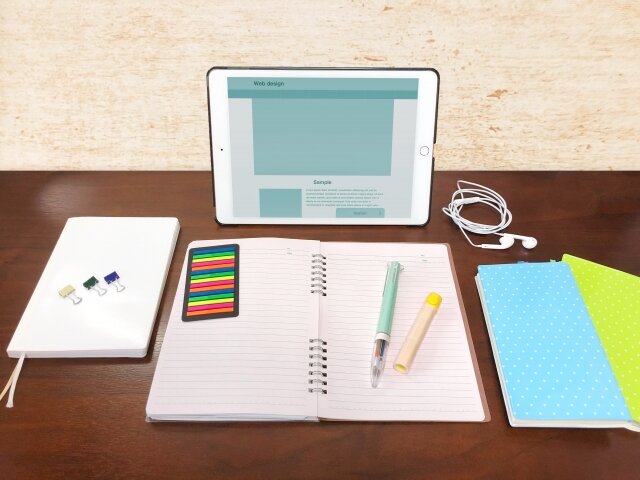アフター/ウィズコロナで学校教育の形が変わる?オンライン授業の「いま」と「これから」
教育
目次[非表示]
新型コロナウイルス感染拡大防止のため全国の小中高校で一斉休校が始まってから約2カ月半。こうした状況の長期化を踏まえ、一部の学校ではすでにオンライン授業が導入・開始されています。今後、緊急事態宣言の解除を受けて登校が始まるようになっても、当面は3密を回避する「新しい生活様式」に沿った教育環境が求められるため、オンライン授業は学校教育の選択肢としてより重要性を増すかもしれません。
では、オンライン授業はどんなふうに行われるものなのか? また、授業を受けるにはどんな環境整備やパパママのサポートが必要になるのか? そこで今回は、中学生と小学生の男の子を育てるNPO法人ファザーリング・ジャパン理事の村上誠さんの体験談を交えながら、オンライン教育の現状と今後のあり方についてお届けします。
では、オンライン授業はどんなふうに行われるものなのか? また、授業を受けるにはどんな環境整備やパパママのサポートが必要になるのか? そこで今回は、中学生と小学生の男の子を育てるNPO法人ファザーリング・ジャパン理事の村上誠さんの体験談を交えながら、オンライン教育の現状と今後のあり方についてお届けします。
【ケース①私立中学校】授業や課題提出を完全オンライン化
村上さんの長男が通う私立中学校でオンライン授業がスタートしたのは、各家庭でのIT環境についての調査や学校側の準備期間を経た4月上旬のこと。通常授業のために学校で購入していたノートパソコンをWi-Fi通信でつなぎ、オンライン授業を受講しているそうです。
「授業は通常1コマ50分のところ、45分に短縮。主な形態として、先生が一方的に講義する大人数での聴講形式と、少人数での双方向形式の2つあります。例えば、数学は学年すべての生徒百数十人が一斉にオンライン授業を受け、学んだ内容についての宿題が出るという流れです。さらに、問題の解き方を解説するYouTube動画を先生が独自に作成し、各自で視聴できるようになっています。一方、英語はクラス単位で授業を行い、個々のコミュニケーションを図りながら進めています」
一方通行の講義だと子どもの理解が追いつくか心配ですが、個別に質問を受け付ける時間が設けられているとのこと。また『Google Classroom』というグループウェアをもともと学校全体で導入しており、課題の出題・提出などオンラインでもコミュニケーションを取りやすい環境が整っているので、先生にとっても生徒にとってもオンライン授業にスムーズに順応しやすかったのでしょう。
また、国語や数学といった学ぶ系の科目以外でも、「技術・デザインではScrachで作成したプログラム動画を提出したり、体育ではエクササイズ動画をお手本にした運動を動画で撮影し投稿しています」など、オンラインの特性を活かした形で授業を進めているそうです。授業の他にも「関数の計算式で絵を描くコンテスト」などオンラインで可能な学びのアイデアが先生から随時紹介されるのだとか。こうしたICT教育への先進的な姿勢は私立校ならではでしょう。
ちなみにオンライン授業を受けているお子さんの感想は「学習内容は理解できるけど、授業が一方通行で進むことや、理科の実験を行えないことには物足りなさを感じている」とのこと。オンライン学習がカバーできる領域に限界があるのは、致し方ないことですね。
「授業は通常1コマ50分のところ、45分に短縮。主な形態として、先生が一方的に講義する大人数での聴講形式と、少人数での双方向形式の2つあります。例えば、数学は学年すべての生徒百数十人が一斉にオンライン授業を受け、学んだ内容についての宿題が出るという流れです。さらに、問題の解き方を解説するYouTube動画を先生が独自に作成し、各自で視聴できるようになっています。一方、英語はクラス単位で授業を行い、個々のコミュニケーションを図りながら進めています」
一方通行の講義だと子どもの理解が追いつくか心配ですが、個別に質問を受け付ける時間が設けられているとのこと。また『Google Classroom』というグループウェアをもともと学校全体で導入しており、課題の出題・提出などオンラインでもコミュニケーションを取りやすい環境が整っているので、先生にとっても生徒にとってもオンライン授業にスムーズに順応しやすかったのでしょう。
また、国語や数学といった学ぶ系の科目以外でも、「技術・デザインではScrachで作成したプログラム動画を提出したり、体育ではエクササイズ動画をお手本にした運動を動画で撮影し投稿しています」など、オンラインの特性を活かした形で授業を進めているそうです。授業の他にも「関数の計算式で絵を描くコンテスト」などオンラインで可能な学びのアイデアが先生から随時紹介されるのだとか。こうしたICT教育への先進的な姿勢は私立校ならではでしょう。
ちなみにオンライン授業を受けているお子さんの感想は「学習内容は理解できるけど、授業が一方通行で進むことや、理科の実験を行えないことには物足りなさを感じている」とのこと。オンライン学習がカバーできる領域に限界があるのは、致し方ないことですね。
【ケース②公立小学校】オンライン教材を使いながら学校の“時間割”に沿って学習
一方、小学校低学年の次男が通っている地元の公立校ではオンライン授業は導入されていないそうです。
「先生からのメッセージや学習内容を解説する動画が学校のホームページ経由などクローズド環境で配信されていますが、オンライン授業というシステム化までには至っていません。現在は、学校が独自に作成した1週間の時間割(1コマ30分を1日5限)とプリント中心のカリキュラムに沿って自宅学習を行っています。また、『NHK for school』の教育番組や教科書出版社などのオンライン動画を見たり、『ジャストシステム』というタブレット学習の学校向けパッケージが市全体で導入されていて、教科書に則したドリルにオンラインで取り組む時間割もあります」
時間割ベースの自宅学習において村上さんが現在悩んでいるのは、特に低学年の子どもには欠かせない親のサポート。「学習の目安になる時間割があるのはありがたいけど、1日に5限も学習するには親の手助けや管理が必要。分からない内容の質問やプリントの答え合わせで仕事が中断されることも多々あり、周りの親からも『在宅で仕事しながら子どもをサポートするのは大変』という声がよく聞かれます」
ちなみに編集部スタッフの娘(小6)が通っている都内の公立小学校では、5月から区の教育委員会が制作しYouTubeにアップした10分前後の授業動画を子どもが“宿題”として視聴(我が家はネットに接続したスマートTVで視聴)。授業動画は単元を細かく分けながら教科書に沿って進められ、また随所で「動画を一時停止して〇〇を調べてみよう」と指示が出され、ただ見るだけでなく子どもも授業に参加しているような構成になっています。
「先生からのメッセージや学習内容を解説する動画が学校のホームページ経由などクローズド環境で配信されていますが、オンライン授業というシステム化までには至っていません。現在は、学校が独自に作成した1週間の時間割(1コマ30分を1日5限)とプリント中心のカリキュラムに沿って自宅学習を行っています。また、『NHK for school』の教育番組や教科書出版社などのオンライン動画を見たり、『ジャストシステム』というタブレット学習の学校向けパッケージが市全体で導入されていて、教科書に則したドリルにオンラインで取り組む時間割もあります」
時間割ベースの自宅学習において村上さんが現在悩んでいるのは、特に低学年の子どもには欠かせない親のサポート。「学習の目安になる時間割があるのはありがたいけど、1日に5限も学習するには親の手助けや管理が必要。分からない内容の質問やプリントの答え合わせで仕事が中断されることも多々あり、周りの親からも『在宅で仕事しながら子どもをサポートするのは大変』という声がよく聞かれます」
ちなみに編集部スタッフの娘(小6)が通っている都内の公立小学校では、5月から区の教育委員会が制作しYouTubeにアップした10分前後の授業動画を子どもが“宿題”として視聴(我が家はネットに接続したスマートTVで視聴)。授業動画は単元を細かく分けながら教科書に沿って進められ、また随所で「動画を一時停止して〇〇を調べてみよう」と指示が出され、ただ見るだけでなく子どもも授業に参加しているような構成になっています。
【ケース③習い事】デジタルツールを介してオンラインレッスン
学校以外の学びの場といえば、習い事。外出自粛で教室まで通えなくなった今、どのような状況なのか?
村上さんの次男が通っているそろばん教室ではオンライン授業がスタートしたものの、「そろばんをはじく手元がカメラにちゃんと映らないので見づらい」のが難点。また、知り合いのお子さんが通っているピアノ教室でもオンラインレッスンを行っているそうですが、こちらも鍵盤を叩く手元が見づらかったり音のタイムラグが生じるなど、課題は山積みのようです。
ちなみに編集部スタッフの娘が通うピアノ教室でもオンラインレッスンを行っていますが、その方法は週1回のLINE経由での動画交換。まず子どもの演奏を保護者が自宅で録画してLINEにアップし、先生が動画をチェック。その内容を踏まえた指導を今度は先生が録画してLINEにアップし、子どもはレッスン動画に従って練習するという流れです。このやり方だと音や映像の乱れというオンラインならではのトラブルも回避でき、また指導内容を何度も見返すことができるので、娘もストレスを感じることなくレッスンを受けられているようです。
村上さんの次男が通っているそろばん教室ではオンライン授業がスタートしたものの、「そろばんをはじく手元がカメラにちゃんと映らないので見づらい」のが難点。また、知り合いのお子さんが通っているピアノ教室でもオンラインレッスンを行っているそうですが、こちらも鍵盤を叩く手元が見づらかったり音のタイムラグが生じるなど、課題は山積みのようです。
ちなみに編集部スタッフの娘が通うピアノ教室でもオンラインレッスンを行っていますが、その方法は週1回のLINE経由での動画交換。まず子どもの演奏を保護者が自宅で録画してLINEにアップし、先生が動画をチェック。その内容を踏まえた指導を今度は先生が録画してLINEにアップし、子どもはレッスン動画に従って練習するという流れです。このやり方だと音や映像の乱れというオンラインならではのトラブルも回避でき、また指導内容を何度も見返すことができるので、娘もストレスを感じることなくレッスンを受けられているようです。
オンライン授業の課題と今後は?
すでに実践している学校で軌道に乗っている例もあるように、学校側と家庭側の環境が整いさえすれば、オンライン授業を行うこと自体は可能でしょう。その一方、子どもの自宅学習を間近で見た村上さんは、オンライン授業の課題や対策を次のように挙げています。
① 子どもが授業に集中して参加できるか
教室という同じ空間で先生とコミュニケーションがとれる学校での授業と違い、一方通行となるオンライン授業は動画を見続けるだけなので、集中力を持続するのはけっこう困難(小学校低学年ならせいぜい20分が限度かも)。
また、小学校の授業の進め方には「先生の説明だけで理解できない子は、周りの子を真似しながら理解する」という側面があり、オンライン授業だと付いていけない子が生じる懸念も。そうした子たちへのフォローが学校や親に求められることでしょう。
また、小学校の授業の進め方には「先生の説明だけで理解できない子は、周りの子を真似しながら理解する」という側面があり、オンライン授業だと付いていけない子が生じる懸念も。そうした子たちへのフォローが学校や親に求められることでしょう。
② オンラインで“社会性”を学ぶことはできるか
教科書に沿った“知識”はオンライン授業で得ることができても、本来クラスでの集団行動を通じて身につけていく“社会性”をオンライン経由で学ぶことは難しそう。
もし今後、学年やクラスごとに時間や日をずらして登校する「分散登校」にシフトしていくなら、知識系の学習はオンライン授業に集中させ、“みんなで集まるからできること”を登校時に優先して行うよう、振り分けていくと良いのではないでしょうか。
もし今後、学年やクラスごとに時間や日をずらして登校する「分散登校」にシフトしていくなら、知識系の学習はオンライン授業に集中させ、“みんなで集まるからできること”を登校時に優先して行うよう、振り分けていくと良いのではないでしょうか。
③ 直接会う機会が減ってしまう子ども同士の交流
3密を回避する「新しい生活様式」は今後も継続する必要があるため、オンライン授業中心の学校教育にシフトすると、以前のように子ども同士が頻繁かつ気軽に会うことは少なくなるかも。中高生ならZoomなどのオンラインサービスで自主的に交流できますが、小さい子は親のサポートが必要でしょう。
ちなみに村上さんの家庭では、Zoomで保護者同伴のオンラインおやつ会を開き、参加した約10人の子どもたちは「こんなつながり方があるんだ!」と驚きながら喜んでいたそうです。
ちなみに村上さんの家庭では、Zoomで保護者同伴のオンラインおやつ会を開き、参加した約10人の子どもたちは「こんなつながり方があるんだ!」と驚きながら喜んでいたそうです。
配信システムの構築をはじめ、公立学校ではまだまだ導入へのハードルが高いオンライン授業ですが、今後一斉休校が解除され分散登校が始まっていく中で、「新しい生活様式」と両立するためにもそのニーズは高まるものと予想されます。そうなると、IT端末や通信環境の整備、さらに自宅学習への取り組みの管理など、学校任せではなく親の関与も必要になるでしょう。
いざオンライン授業が始まる時にあわてないよう、ICT教育の今後の推移を注意深く見守りながら、適切なサポート体制の準備に努めていってはいかがでしょうか。
▼あわせて読みたい
いざオンライン授業が始まる時にあわてないよう、ICT教育の今後の推移を注意深く見守りながら、適切なサポート体制の準備に努めていってはいかがでしょうか。
▼あわせて読みたい