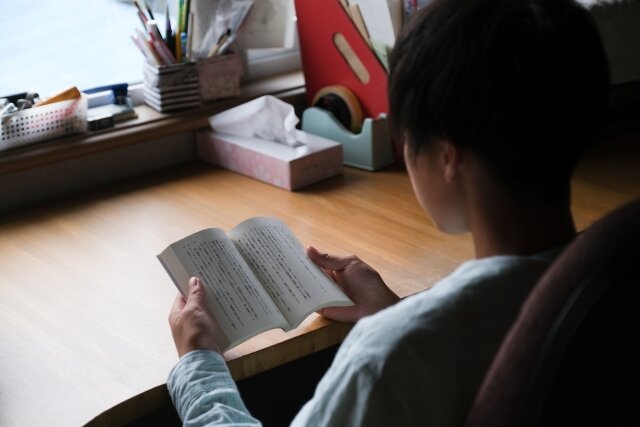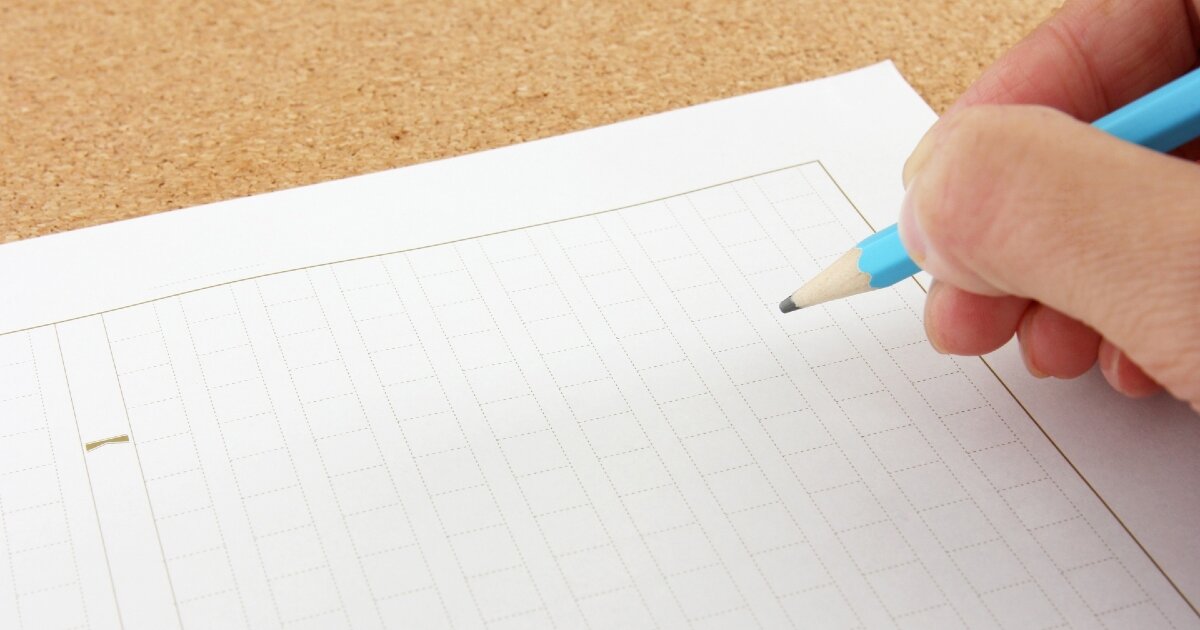
【読書感想文の書き方】文章のプロが子どもたちにアドバイス!夏休みの読書感想文がスラスラ書けるコツ
教育
目次[非表示]
※この記事は2020年8月公開の記事を再編集・再公開しています
子どもの夏休みの宿題、手こずってしまう・最後まで残ってしまうものとは…?
コロナ禍の影響もありつつ、今年も全国の学校で夏休みが始まりました。ドリルやプリントなどの学習系も大変ですが、夏休みの宿題で子どもが特に手こずるものといえば「読書感想文」。
株式会社イオレが2019年に行ったアンケート調査(※)でも、最後まで残りがちな宿題として読書感想文がトップ。長い文章を書き慣れていない子どもたちにとって、感想文を書くことがいかに苦手か伺えます。
※「夏休みの宿題」ついつい手伝ってしまうのは親の本能?最後まで残るのは毎年“読書感想文”!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000030850.html
株式会社イオレが2019年に行ったアンケート調査(※)でも、最後まで残りがちな宿題として読書感想文がトップ。長い文章を書き慣れていない子どもたちにとって、感想文を書くことがいかに苦手か伺えます。
※「夏休みの宿題」ついつい手伝ってしまうのは親の本能?最後まで残るのは毎年“読書感想文”!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000030850.html
そんな悩める子どもたちをサポートすべく、普段から雑誌やWEBなど幅広い媒体で記事を執筆している編集部スタッフが、学校では教えてくれない「読書感想文がスラスラ書けるようになるコツ」を紹介しましょう。
これを押さえればOK!読書感想文の基本構成4ポイント
読書感想文は「先生への紹介・プレゼン」
子どもが読書感想文を苦手とする最大の理由、それは「何を書いたらいいか分からない」に尽きるのではないでしょうか(本を読むのが面倒くさいという気持ちは、いったん横に置いておきます)。逆に言うと、何を書けばいいかさえ分かれば、その内容を順々に書き進めることで原稿用紙は一気に埋まります。
雑誌の記事でも会議のプレゼン資料でも、どんな文章でもそこには“読者(読んでほしい人)”が存在します。そして「読者は何を知りたいか」「何を書けば興味を持ってくれるか」を考えることで、どんな文章を書けばいいか一定の方向性が定まっていきます。
では、読書感想文の読者とは誰でしょう? そう、感想文を提出する学校の先生です。つまり、自分が読んだ本の内容や面白さを、読んだことのない先生に説明・紹介(プレゼン)するつもりで書くことが、読書感想文の基本フォーマットと言えるでしょう。
雑誌の記事でも会議のプレゼン資料でも、どんな文章でもそこには“読者(読んでほしい人)”が存在します。そして「読者は何を知りたいか」「何を書けば興味を持ってくれるか」を考えることで、どんな文章を書けばいいか一定の方向性が定まっていきます。
では、読書感想文の読者とは誰でしょう? そう、感想文を提出する学校の先生です。つまり、自分が読んだ本の内容や面白さを、読んだことのない先生に説明・紹介(プレゼン)するつもりで書くことが、読書感想文の基本フォーマットと言えるでしょう。
【構成①】「なぜその本を選んだか」を書く
読書感想文でつまずきやすいのが、冒頭の書き出しですよね。そこで、先ほど触れた「先生に向けて書く」というコンセプトに立ち返ってみましょう。
先生が生徒の読書感想文でまず知りたいのは、なぜその本を選んだかということ。「タイトルがユニークだったから」でも「最近、ニュースで話題になっていた出来事と関連があり興味を惹かれたから」でも、なんでも構わないのでその理由を書き出しで表してみましょう。
先生が生徒の読書感想文でまず知りたいのは、なぜその本を選んだかということ。「タイトルがユニークだったから」でも「最近、ニュースで話題になっていた出来事と関連があり興味を惹かれたから」でも、なんでも構わないのでその理由を書き出しで表してみましょう。
【構成②】あらすじの要約を書く
本を選んだ理由を導入パートとするなら、その次に続く読書感想文の軸となる部分こそが「あらすじの要約」。なぜかというと、読んだことのない先生に向けて本を紹介するには、おおまかなあらすじを説明することが必要だから。あらすじを書くことは、決して原稿用紙の文字数を稼ぐためだけのものではないのです。
ただし、あらすじを延々と羅列していくだけだとまとまりがつかなくなるので、5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どうやって)を意識しながらコンパクトに要約するといいでしょう。
ただし、あらすじを延々と羅列していくだけだとまとまりがつかなくなるので、5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どうやって)を意識しながらコンパクトに要約するといいでしょう。
【構成③】「読んで何を感じたか」を書く
書評であれば「この本はここが読み応えある」「この描写にはこんな意味が込められている」といった深い洞察がオリジナル要素として求められますが、読書感想文においては「読んで何を感じたか」「どんな発見(気づき)を得られたか」を書けば十分であり、真に求められていること。
面白かったところ、驚いたところ、感動したところ、共感したキャラクター、大切さに気づいたこと…。自分の心に残ったさまざまな思いを、「面白かった」で終わらせず「なぜ面白いと感じたのか」という理由まで含めて書けば、おのずと読書感想文らしい形に整います。その際、感じたことをひと通り羅列してしまうと収拾がつかなくなるので、絶対伝えたい主要ポイントを3~4つまでに絞るといいでしょう。
面白かったところ、驚いたところ、感動したところ、共感したキャラクター、大切さに気づいたこと…。自分の心に残ったさまざまな思いを、「面白かった」で終わらせず「なぜ面白いと感じたのか」という理由まで含めて書けば、おのずと読書感想文らしい形に整います。その際、感じたことをひと通り羅列してしまうと収拾がつかなくなるので、絶対伝えたい主要ポイントを3~4つまでに絞るといいでしょう。
【構成④】「読んで感じたことのまとめ」を書く
読書感想文の最後は、①~③で書いてきたことのまとめで締めくくります。
冒頭で書いた「なぜその本を選んだか」という理由と照らし合わせ、「手に取った時はこう思ったけど、実際に読んで見るとこう感じた」と感想の変化を書くもよし。あるいは、読んで感じたことと呼応する形で「この本を読んで今後こうしようと思った」と心の成長を表明するもよし。前段までの内容と連動させると、締めくくりに書く内容が思いつきやすいし、読書感想文の全体に一貫性が出て完成度もアップしますよ。
冒頭で書いた「なぜその本を選んだか」という理由と照らし合わせ、「手に取った時はこう思ったけど、実際に読んで見るとこう感じた」と感想の変化を書くもよし。あるいは、読んで感じたことと呼応する形で「この本を読んで今後こうしようと思った」と心の成長を表明するもよし。前段までの内容と連動させると、締めくくりに書く内容が思いつきやすいし、読書感想文の全体に一貫性が出て完成度もアップしますよ。